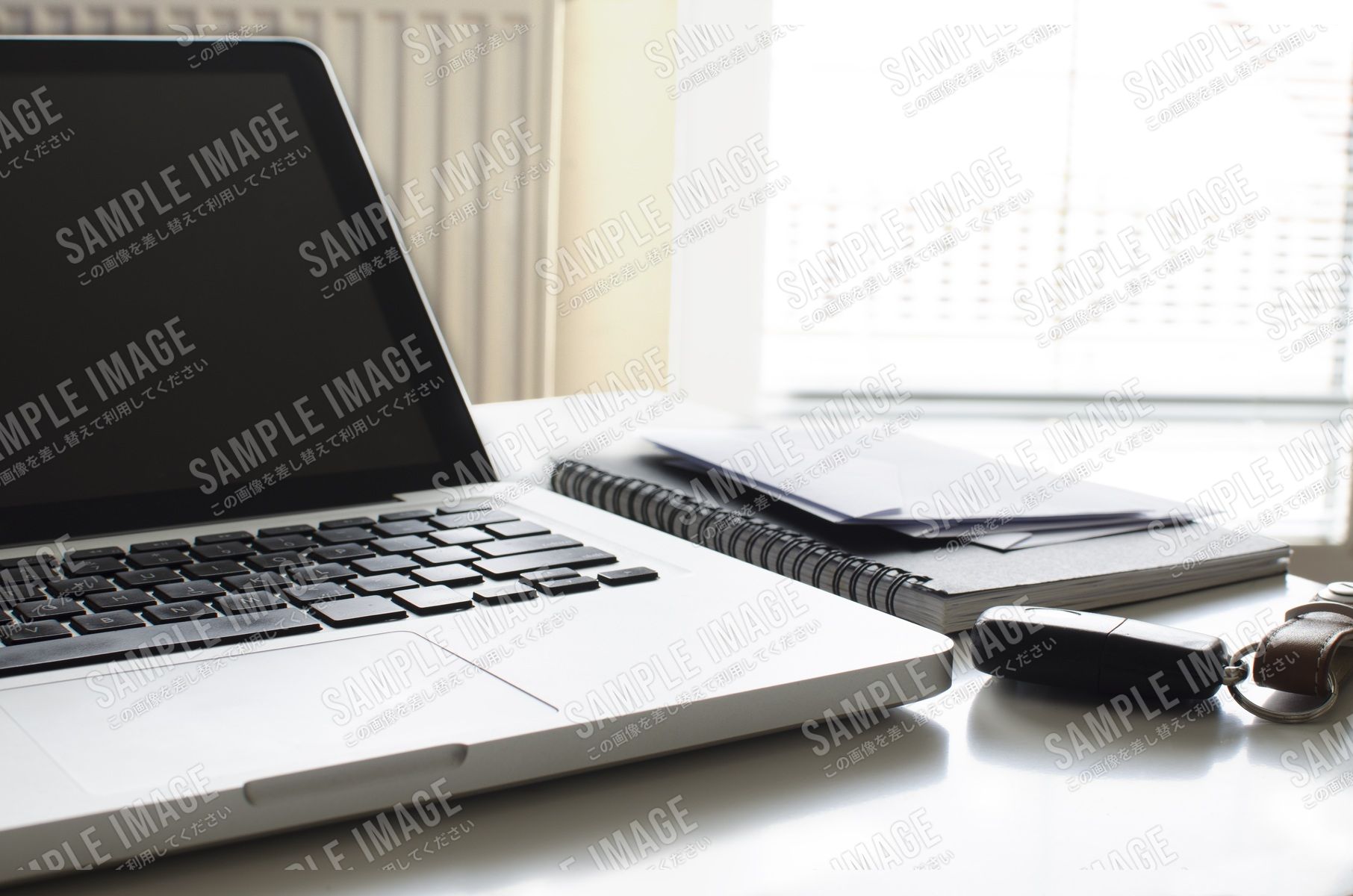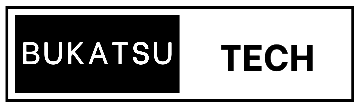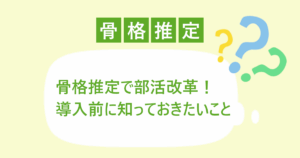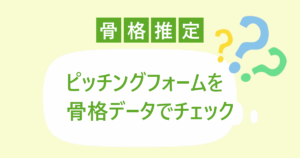陸上部に骨格推定を導入!スタートからフォーム改善まで
陸上部に骨格推定を導入!スタートからフォーム改善まで
近年、AI技術の進歩により、スポーツの現場でもさまざまなテクノロジーが活用されるようになってきました。その中でも注目を集めているのが「骨格推定」です。この記事では、陸上部の練習や試合で骨格推定技術を導入するメリットや活用方法、実際のフォーム改善への具体的な流れについてご紹介します。
骨格推定とは?
骨格推定とは、カメラやスマートフォン、PCなどのデバイスを使って人の関節や骨格の位置をAIが自動的に推定し、デジタル上で可視化する技術です。最近では、MediaPipeやOpenPose、OpenPifPafなど、オープンソースの骨格推定ツールも増えており、専門的な機材がなくても簡単に利用できるようになっています。
陸上競技でなぜ骨格推定が必要?
陸上競技は、わずかなフォームの違いがタイムや記録に大きく影響します。しかし、従来の指導方法では「感覚」や「見た目」に頼ることが多く、正確な改善ポイントを特定するのが難しい場合がありました。骨格推定を導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- 客観的なデータによるフォーム分析
骨格推定によって得られた関節角度や動作の軌跡は、すべて数値化されます。これにより、選手自身や指導者が感覚ではなく、客観的なデータに基づいてフォームを評価・改善できます。 - 成長の可視化
時系列でデータを蓄積することで、フォームの変化や成長をグラフや動画で確認できます。これが選手のモチベーションアップにもつながります。 - 怪我予防・パフォーマンス向上
無理な動作やアンバランスなフォームを早期に発見できるため、怪我の予防やパフォーマンス向上にも役立ちます。
骨格推定の導入例 ~スタートダッシュの解析~
陸上競技の中でも、特に重要とされるのが「スタートダッシュ」です。スタートの一瞬でその後のタイムが大きく左右されるため、多くの選手や指導者がフォーム改善に頭を悩ませています。
例えば、スタート動作をスマホのカメラで撮影し、骨格推定ツールを使って各関節の動きや角度を可視化します。具体的には以下のような流れです。
- 撮影
スタート時の動作を横や斜め前方から撮影します。 - 骨格推定ツールで解析
撮影した映像をMediaPipeやOpenPoseなどで解析し、肩・肘・膝・足首などの関節角度や動作のタイミングを抽出します。 - データの比較・分析
理想のフォームや自己ベスト時のデータと比較し、「膝の角度が浅い」「腕の振り出しが遅い」など、具体的な課題を数値で把握します。 - フィードバックと改善
分析結果をもとに、練習メニューを調整したり、意識するポイントを伝えたりして、繰り返しフォーム改善を図ります。
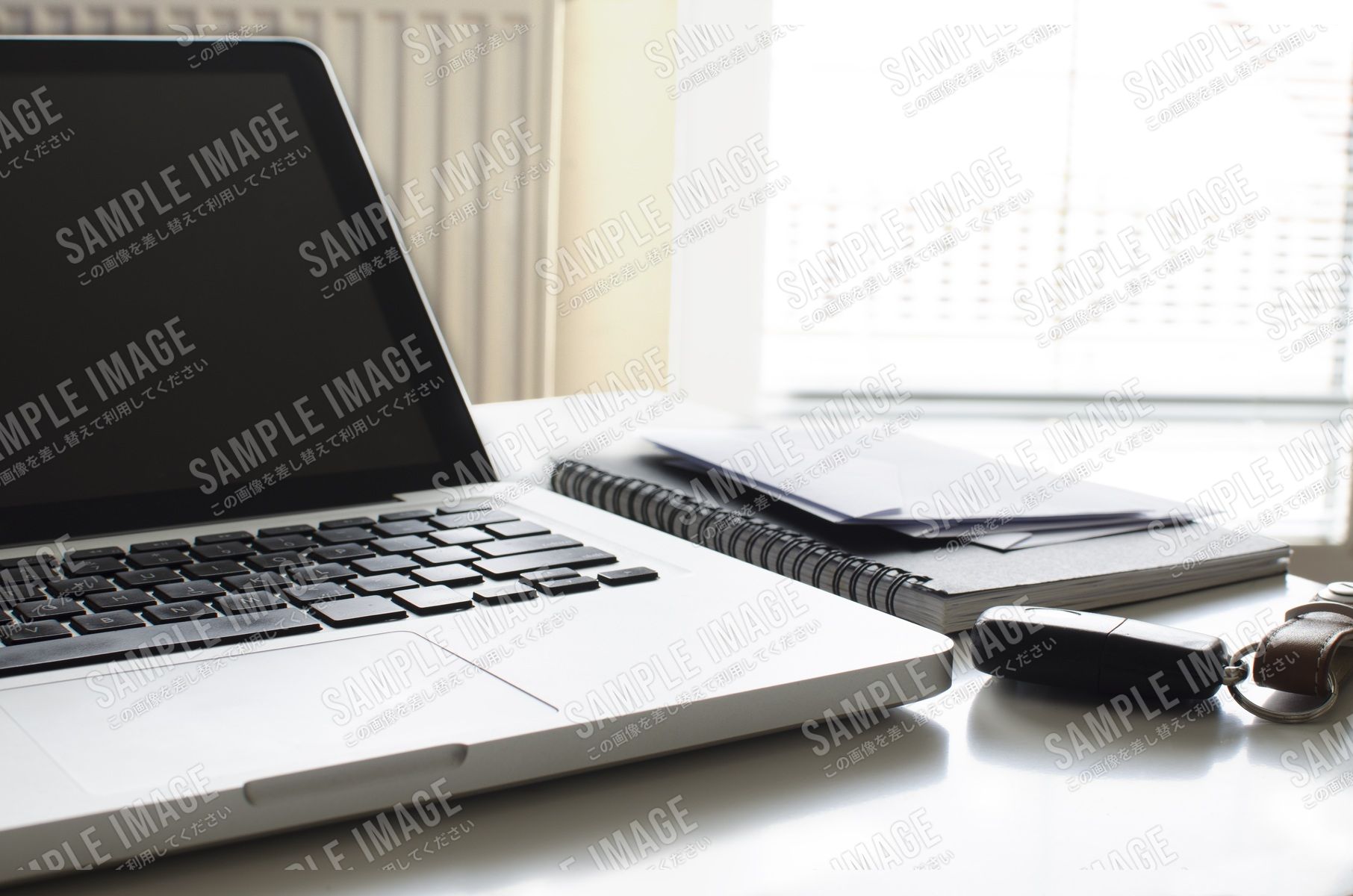
今すぐ無料で試してみる!
ハードルや走り幅跳びでも効果を発揮
骨格推定は、短距離だけでなく、ハードルや走り幅跳びなど複雑な動作を必要とする種目でも大きな効果を発揮します。例えば、ハードルの踏切時の膝や股関節の角度、空中動作中の腕振り、着地時の姿勢など、これまでは見落としがちな細かい動作まで数値でチェックできます。
実際の現場でどう使う?導入のポイント
「技術的に難しそう…」「コストがかかりそう」と感じるかもしれませんが、現在は無料や低価格で使える骨格推定アプリやウェブサービスも多く登場しています。
また、スマホやタブレットでも十分な解析が可能なので、気軽に導入できます。
導入の際は、
- データの取り方を統一する(撮影角度や距離)
- 解析したデータを記録・蓄積する
- 選手ごとに目標や課題を明確にする
などのポイントを意識すると、より効果的に活用できます。
まとめ
骨格推定は、陸上競技のフォーム改善や怪我予防、パフォーマンス向上に大きな可能性を持った技術です。スタートダッシュや跳躍動作など、目に見えない細かな部分まで可視化し、客観的なデータとして選手や指導者に提供してくれます。これからの陸上部活動に、ぜひ骨格推定を取り入れてみてはいかがでしょうか。